フリーランスを目指す人たちの間で話題になっている「フリキャリ」ネットで検索すると「怪しい」という言葉を目にすることもあります。でも、実際のところはどうなのでしょう。副業や独立を考えている人であれば、スクール選びに慎重になるのは当然です。
高い料金を払うわけですから、その価値が本当にあるのか、運営会社は信頼できるのか、受講後の成果は期待できるのか——こうした疑問を持つのは自然なことです。私たちは、フリキャリについて、実際の口コミや公開情報をもとに、一度しっかり検証してみることにしました。新興企業だからこそ、先入観ではなく、実態を知ることが大切です。
実際の評判はどうなのか?
フリキャリに対して「怪しい」という検索をする人が一定数いるのは事実です。その背景には、いくつかの理由があります。まず、UNARI株式会社は2025年8月に設立された比較的新しい企業です。
スクール業界では古参の企業が信頼を集めやすいので、新興企業に対する警戒心が自然と働きます。それ自体は悪いことではなく、むしろ受講者が慎重に選択している証だと言えます。
料金は無料相談で個別提案される仕組みになっています。これは企業側の戦略としては理解できますが、受講者にとっては透明性に欠けると感じるかもしれません。「相談に行ったら営業されるのでは?」という心配も、自然な疑問です。
さらに、フリーランス養成スクール自体が、従来の通信講座や大学のような「確立された形態」ではありません。だからこそ、「実際に稼げるのか」「本当に案件をもらえるのか」という疑問が生まれやすいのです。ただし、ここで重要なポイントがあります。
「新しい」=「怪しい」ではなく、「未知」だからこそ、自分で確認する必要があるということです。
実際の受講生の声から読み取る成果と課題
公式サイトに掲載されている受講生の事例を見てみましょう。大学3年生の男性はSNS運用スキルを身につけ、就職活動で差別化に成功しました。大学4年生の女性は動画編集案件で月10万円の収入を実現しています。
これらの事例に共通する特徴は、個人の主体性と学習時間の確保が前提になっているという点です。公式の説明では「やり方次第で実現可能」と明記されています。これは誠実な表記だと言えます。
スクールが「やれば誰でも成功する」と謳わずに、受講者側の努力が必要であることを認めているからです。良い口コミには「現役フリーランス講師による1対1指導」「質問し放題」「案件提案から納品フローまで実践的に学べる」といった点が挙げられています。これらは、動画見放題型のスクールには得られない価値です。
一方で、懸念点もあります。新しいサービスであるため、長期的な実績や第三者によるレビューが少ないこと。そして、受講者が自己管理できなかったり、学習時間を確保できなかったりすれば、期待した成果に到達しないというリスクが存在することです。
UNARI株式会社が提供するフリキャリの実像
では、フリキャリそのものについて、実態を見ていきましょう。
フリキャリが提供するのは、オンライン完結型の実践スクールです。学べるジャンルは、動画編集(YouTube編集、ショート動画、サムネイル制作)、SNS運用(リサーチ、数値分析、アカウント設計)、AIスキル、オンライン秘書業務など、現在の市場で需要が高い領域ばかり。新興企業にもかかわらず、一定の受講者が集まっているのは、市場ニーズに応えた設計になっているからだと考えられます。
フリーランスやオンライン副業で稼ぎたい人の実際の需要と、スクールの内容がマッチしているということです。
伴走型サポートと従来の動画講座の違い
フリキャリの最大の特徴は、伴走型のサポート体制です。単なる動画視聴ではなく、現役フリーランス講師による1対1指導、質問し放題、実案件への挑戦支援まで含まれます。これは「学習→案件化→キャリア相談」まで一気通貫で支援する、という独自のアプローチです。
動画教材で知識を得るだけでなく、実際に案件を取ってみて、納品フローを経験し、提案文の書き方まで指導されるわけです。この伴走型のサポート体制がある分、料金は高めになります。スタンダードコースで6ヶ月、総額約55万円。
フリーランスコースで8ヶ月、総額約80万円という価格設定です。分割払い(36回分割など)も可能ですが、それでも月額数万円の投資になります。価格の高さに対して「それだけの価値があるのか」という疑問は自然です。
その答えは、「個人差が大きい」というのが現実的な返答です。
評判を左右する2つの要因
フリキャリに対する評価がバラつく理由は、実は明確です。
成果が「個人差」に左右されるリアルな実態
スクール側も公式に「個人の努力や学習時間の確保が前提」と明記しています。これは、期待値を正当に設定する上で、非常に誠実な表記です。しかし現実的には、同じコースを受講した人でも、成果に大きな差が出ます。
それは学習時間の確保状況、元々のスキルレベル、モチベーションの維持、そして「行動に移すかどうか」という要因に左右されるからです。「スクール=成功への道」ではなく、「スクール=成功の可能性を高めるツール」という理解が必要です。
口コミが少ない新サービスへの不安
2025年8月設立という背景から、まだ卒業生の実績や長期的な口コミが少ないのは事実です。SNSやレビューサイトで多くの体験談を見つけるのは難しいでしょう。これは「実績不足=信頼できない」という短絡的な判断につながりやすいです。
ただし、言い換えれば、「これからの成長段階のサービス」ということでもあります。古いサービスの安定性と、新しいサービスの市場適応性は、異なる価値です。重要なのは、自分で直接、無料相談で質問してみることです。
講師の対応、質問への返答の丁寧さ、実際のサポート体制の詳細——これらは説明から判断できます。
フリキャリが本当に向いている人・向いていない人
ここまでの情報から、自分に適したサービスかどうかを判断する基準が見えてきます。
成功するための必須条件とは
フリキャリで成果を出している人には、共通の特性があります。第一に、3~6ヶ月の学習時間を自分で確保できる人です。 スクールのカリキュラムは用意されますが、実行するのは受講者自身。
週に何時間、継続的に学習できるかが成否を分ける要因になります。第二に、学習後すぐに実案件へ踏み出したい人です。 フリキャリの価値は、知識習得だけでなく「案件化」にあります。
学んだスキルを実際に使ってみる気がない人には、向きません。第三に、キャリアパスを重視する人です。 スクール卒業後のキャリアについて、真摯に考える。
その過程で講師との相談を活用できる人は、伴走型サポートの価値を感じやすいでしょう。そして基本的に主体的に学び続ける気持ちがある人。これが最も重要です。
失敗リスクを高める特性
逆に、以下に当てはまる人は、期待した成果を得られにくいかもしれません。「最安の学習サービスのみを探している」「受動的な学習で成果を求める」「短期間で高単価を確約してほしい」「自己管理が苦手」「学習時間の確保が難しい」——これらの条件では、投資対効果が合いません。特に重要なのは、「受動的な学習で成果を求める人」です。
スクールは環境を提供するだけで、実際に成果を出すのは受講者です。この認識がないと、「受講したのに成果が出ない。スクールが悪い」という結論に至りやすくなります。
フリーランス支援の実態から見える業界トレンド
フリキャリのような新型スクールが出現・成長している背景には、働き方の多様化があります。従来の動画見放題型スクールは知識習得には向いていますが、実案件との結びつきが弱いという課題がありました。一方、個別コンサルティングは高額で敷居が高い。
その間をつなぐのが、伴走型の中程度の規模のスクールというポジショニングです。市場として「実践的に学びたい」「案件まで結びつけたい」という需要があるから、こうしたサービスが成立するわけです。
スクール選びで本当に大切な判断軸
「このスクールは信頼できるのか」を判断する際、どこを見ればよいのでしょう。設立年数や企業規模は、確認項目の一つに過ぎません。むしろ重要なのは、講師の実績と質、サポート体制の具体性、受講生との相互作用です。
公式サイトの記載内容だけでは限界があります。無料相談を活用して、講師の対応を直接確かめる、質問への返答の丁寧さを感じる、カリキュラムの詳細を聞く——こうした直接的な接触が、判断の精度を高めます。
情報不足を補う、自分で確認すべきポイント
外部の口コミや評判が少ないなら、自分で直接確認することが大切です。
現役講師は本当にいるのか、その実績は何か
受講後のサポートはどこまで続くのか
案件提案は実際に行われるのか、どの程度の単価か
学習期間中、平均的な学習時間の目安は何時間か
受講生の自己管理が不十分だった場合、どうサポートされるのか
これらを具体的に質問すれば、企業側の誠実さが伝わってきます。逆に、曖昧な返答しかない場合は、信頼度が下がると考えてよいでしょう。
まとめ
フリキャリが「怪しい」と言われるのは、新興企業であること、料金体系の透明性が十分でないこと、第三者レビューが少ないことが理由として挙げられます。これらの理由は、警戒心を持つ根拠としては妥当です。しかし、同時に「新しい」ことと「怪しい」ことは別です。
スクールの質は、企業の歴史ではなく、実際のサポート体制と講師の質で判断すべきです。フリキャリは、伴走型のサポートに特化した、市場ニーズに応えた設計になっています。主体的に学べる人、実案件への挑戦を望む人にとっては、確実な価値が期待できます。
一方で、受動的な学習を求める人や、学習時間を確保できない人には、投資効果が限定的になるでしょう。「怪しい」という疑問は、スクール選びの前提として大切です。その疑問を解くために、まずは無料相談を活用する。
講師に直接質問し、自分の目と耳で判断する。これが、後悔しないスクール選びの唯一の方法です。フリーランスへの道は、スクールだけで開かれません。
スクールはあくまで、その可能性を高めるきっかけに過ぎません。「自分は本気でこの道に進みたいのか」「3~6ヶ月、継続的に学習できるのか」——その問いに自分で答えてから、スクール選びをするべきです。
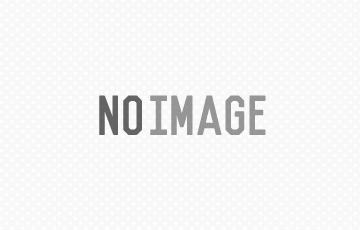
コメントを残す